第53回 2019.01.22
尾駮の駒・牧の背景を探る発行元: 六一書房 2018/07 刊行
評者:小口雅史 (法政大学教授・同国際日本学研究所所長)
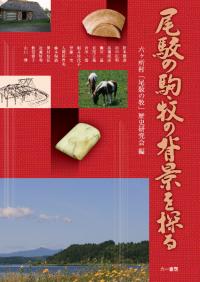
尾駮の駒・牧の背景を探る
著書:六ヶ所村「尾駮の牧」歴史研究会 編
発行元: 六一書房
出版日:2018/07
価格:¥2,750(税込)
目次第一部 考古学的考察
松本建速 六ヶ所村に馬はいつからいたか?
田中広明 東北地方北部出土の石帯とその背景
高橋照彦 東北地方北部出土の緑釉陶器とその歴史的背景
瀬川 滋 コラムI 陸奥湾東岸域(野辺地地区)の環濠集落
長尾正義 コラムII 三沢市「平畑(1)遺跡」の特徴について
第二部 歴史学的考察
倉本一宏・堀井佳代子 藤原道長と馬、そして尾駮の駒
伊藤一允 建武期の糠部と尾駮の牧
入間田宣夫 「尾駮牧」「糠部駿馬」をめぐる人・物・情報の交流について
藤木保誠 コラムIII 平安時代の都の馬事情
栗村知弘 コラムIV 糠部郡内の十烈、流鏑馬
近藤好和 コラムV 日本前近代の馬
第三部 文学的考察
飯沼清子 平安貴族と馬
山口 博 ユーラシアを西から東へ駆けた斑動物たち、そして尾駮の駒へ
山口 博 歌語“尾駮の駒”を育んだ王朝歌人集団
山口 博 王朝歌人の陸奥心象風景と現実
飯沼清子 コラムVI 巡方瑪瑙帯とその後
まえおきとして
本書は、古代の歌枕の一つである「尾駮」(おぶち)の地名が現存する青森県六ヶ所村(古代以来の馬産の歴史も有する)の「尾駮の牧」歴史研究会が、その歴史的背景を解明すべく、2012年より実に6年間にわたって開催し続けた「六ヶ所村歴史フォーラム」の成果を、考古学的考察、歴史学的考察、文学的考察の3部に再編して一書にまとめなおしたもの。
当村に限らず、文献史料がほとんど残存しない北奥地域の古代を解明するのは至難の業であるが、自らは黙して語らないものの多くの考古学的成果があり、加えてわずかに残された文献的痕跡とその後の歴史的展開を踏まえての考察が、それぞれ縦糸・横糸となり、当該地域の豊かな歴史像を描き出している労作である。
評者の弘前大学在任期は、ちょうど青森県内の自治体史編纂が盛んに行われた時期であったこともあり、爾来、多くの自治体史編纂に関わってきた。とくにもっとも時間と労力を要したのが戦後初の編纂となる『青森県史』である。古代部会長として関わった古代資料編では、多くの研究者の協力をいただいて、出土文字資料までをも含めた関係史料の博捜と集成をはかり、また通史部会長として関わった通史編では、これまた新進気鋭の研究者から大家の先生方まで第一線の研究者を揃えて、資料編に基づく青森県の古代〜中世期の歴史的展開を描いた。
しかしながらその通史のなかには古代の尾駮の牧も尾駮の駒も登場しない。六ヶ所村の皆さんには申し訳ないかぎりである。わずかに和歌を中心とした文学作品に見える「おぶち」史料が数点『青森県史資料編古代1補遺』のなかに採録されているのみである。そしてそれが通史に利用されることはなかった。つまり歌枕としての尾駮の牧も尾駮の駒も、その存在を明確に認識していながら、通史の記述にそれを生かせなかったということである。
それはいったいなぜなのか。理由は明確である。歌枕にみえる地名が現存しているとき、もし古代の史料が歌枕以外無いとすれば、現在の地名を古代まで遡らせることができるかどうか分からないからである。これはよく知られていることであるが、現在の宮城県域や岩手県域には歌枕に由来する地名がかなり見られる。これは近世期に各地で展開された名所整備運動の結果であって、盛岡藩も仙台藩もそうした事業に熱心であった。例えば芭蕉の『奥の細道』にも「尾ぶちの牧」が登場し、それは現在の宮城県石巻市内である。青森県に例をとれば「つぼのいしぶみ」が著名であるが、東北町にそれに相当するとされる「日本中央」碑がある。しかしながら東北町〜七戸町には、「坪」「千曳」「石文」という地名がほぼ等距離の3角形上に配置されている。あまりにできすぎているのである。歌枕研究の第一人者の一人金澤規雄は、これも盛岡藩の名所再整備運動の結果であると力説している。そもそも「つぼのいしぶみ」は実在しない幻の碑なのだから。先般、おいらせ町に招かれて(阿光坊古墳の史跡整備委員を務めさせていただいたご縁である)この件をお話したとき、猛烈な反発があるかと覚悟していたのであるが、おいらせ町の皆さんはじつに冷静に聴いておられたので、かえってこちらが感動したくらいである。
日本古代国家の北進により、北方世界の情報が都にも届くようになり、実態に即した歌枕ももちろん生まれた。日本古代史の側からの研究としては例えば渕原智幸によるものがある。しかしたとえば「えぞがちしま」(現在の千島列島の語原。ちなみに北海道に『日本書紀』中の阿倍比羅夫北征に因む地名がたくさんあるのは、探検家松浦武四郎の命名による)は完全に空想の産物である。
もちろん県史執筆に当たってはそれなりの冒険もしたし、使えるものは出来るだけ使うようにした。ただ「尾駮」については残念ながら自信を持ってそれに触れるだけの素材を、私自身の力量不足もあって、見出せなかったのである。
津軽地方だと、南部家文書にみえる地名に由来するとされるものが多数残されていて、そこに記載された地名を現在の類似地名と比較することは容易にできる。確かに中世の地名が現在までよく残っていることは明白である。しかしながら六ヶ所村の尾駮については、近世の正保期までしか遡れなかった。もちろん史料がないからといってそれが近世の地名だと断定することはできない。史料はないだけでさらに遡る可能性は常にある。ただ歴史学者としては根拠史料無しに触れることはやはりできなかったのである。
本書を読む前の評者を取り巻く尾駮についての研究状況は、以上のようなものであった。
本書の内容
まえおきがずいぶん長くなってしまったが、これは評者に限らず、おそらく日本古代北方史研究における常識的なスタンスは、以上のものであるはずである。『青森県史』通史1に尾駮の牧が描かれなかった事情は分かっていただけたと思う。
さて本書を読み終えて、これまでのこうした研究史上の常識的スタンスがどう変わるか、である。さっそく本書の内容を順にみていこう。
文献史料が残されていない場合、一番頼りになるのが考古学資料である。当地に限らず北方史研究史上において考古学の果たす役割はきわめて大きい。学界で北方史研究が文献史学と考古学のコラボのモデルとされている所以である。当然本書も考古学から切り込むことになる。第一部は考古学的考察で3本の論文と2本のコラムを収める。
第一部冒頭の松本建速論文「六ヶ所村に馬はいつからいたか?」は、本書の基調となる重要なもの。馬産に関わる土壌としてよく知られている黒ボク土を主たる根拠として、六ヶ所村の地に、9世紀後葉に馬の飼育をする人々が移住してきたことを推定する。そして以後も馬の飼育が継続された。この結論自体には高い可能性が認められると思う。当地は馬産地であったといって良い。ただしつこいようであるが、そのことと和歌の歌枕尾駮がこの地だと言うこととは別問題とせざるをえないことには注意が必要である。
また細かいことをいえば、もし私がフォーラムの現場にいたら、挙手して著者に聞いてみたかった論点がいくつかある。私が基本的に文献史学者であるからであるが、文献史料や律令ほか法制史料の使い方に、いくつか違和感を覚えた。一つだけ例を挙げれば、養老厩牧令11牧地条の規程をそのまま実態に直結させているが、この条文は母法である唐令の丸写しであることが寧波の天一閣で発見された天聖令によって確実になっている。さらに天聖令云々とはかかわらず、そもそも律令と実態との関係は慎重な検討が必要である。もちろん氏の行論に大きな影響を与える話しではないので、ここではこれ以上の深入りはしない。
北奥の馬産について一番に気になるのが、この名馬がどこから来たという点であろう。本論文では馬産集団の移住が想定されているが(人がどこから来たのかについても今回は保留している。五所川原産須恵器を持つ人々とだけ述べている。ただ五所川原産須恵器が出土する地の人が馬産に携わった人だという説明が分かりにくくなっている)、名馬はどこから来たのであろうか。本書第二部の近藤好和「コラムV日本前近代の馬」では、糠部駿馬も日本南部の馬と同じく朝鮮半島から入った蒙古野馬の系統とされている。実証されたことではないが、北方史研究の大家新野直吉は、北の馬(海)道論を提唱していた。北回りでの(北海道を飛び越えての)馬の渡来である。先般、毎日新聞青森版の拙稿「青森県史の玉手箱」でも触れたが、最終的には県内出土の馬の骨のDNA鑑定が期待される。聞くところでは奈良文化財研究所などの研究グループが動き出しているので、この問題についてはその成果を待ちたい。ただ本論文では馬がいたことを示すランクAの資料は馬具だとされているが、馬がいたことを示すランクAの資料は馬の骨ではないのだろうか。あるいは馬骨は野生その他別要素があり得るので人為に配慮したということか。第2表が東北北部の馬骨の一覧表であるが、行論中ではこの表は使用されていない。しかもこの表では津軽側に出土例が多いのも気になるところである。
関連して青森県内ではこれまでもしばしば論点になっている(本人も行論中で一度だけ示唆している)、7世紀以前の古い時代の遺構が見つかっていない(津軽ではさらに8世紀になってもはっきりしない)ことが、そのまま人がいなかったことになるのか。遺構の立地や構造が違うから見つからないだけではないのか、という点についても説明がほしかった。
ただこれらは一般向け講演と言うことで、私自身もしばしばそうするように、意図的に深入りしなかっただけのことかもしれない。
ちなみに古代の牧といえば甲斐国がすぐに想起されるが、その甲斐でも馬の生産がいつから始まったかはまだはっきりしていないという。河内国の馬飼集団に関係するとのことであるが(大隅清陽『古代甲斐国の交通と社会』六一書房)。望月牧で著名な隣国信濃国(ここは私の郷里である)も似たような状況である。こうした古代に牧が置かれた他の国との比較史的研究も期待される。
ついで田中広明「東北地方北部出土の石帯とその背景」、高橋照彦「東北地方北部出土の緑釉陶器とその歴史的背景」が続く。石帯・緑釉陶器と、高級品が当地で出土している意味を探りながら馬産の背景に迫る。
田中論文は六ヶ所村表館遺跡出土の石帯を、平安京で作られた白玉帯の蛇尾であるとし、長さと幅の比率により9世紀末から10世紀の製作とする。高橋論文は古代における高級陶器である緑釉陶器について、東北北部全体を見回した分布と青森の分布を比較し、青森の緑釉陶器が城柵などを通じての交易だけではなく、より私的な富裕の輩による(なお高橋論文で用いられている「富豪層」という表現は、歴史学においては特殊な定義がなされる学術用語なので避けた方が良い)私的な交易の広がりの結果であるという。田中も高橋も都人と六ヶ所村の人々が直接接触する特殊な経路があり、平安京ともつながる遠距離交易の可能性を示唆する。これは第二部の入間田宣夫論文でも特殊ルートの存在として支持されているところである。そしてその意味するところは、おのずと馬産の対価として!ということになる。瀬川滋・長尾正義のコラムもそれを補強する。もちろん田中は明言していないし、高橋自身も証明はされていない、あくまで可能性にとどまるとしているが。
私の感想を少しだけ述べさせていただくと、田中が、渡嶋津軽津司と大川遺跡をつなげるのは通説を超えた大胆な推定で、古代へのロマンを大いにかきたてる。ただ田中をはじめ誰も触れていないが、同じ時期に津軽側の五所川原市の観音林遺跡でも石帯が出土している。これとの関係はどうなるのであろうか。単純に下北方面のルートだけではない様相がみえている。
また田中は八戸市丹後平古墳出土の鉄製腰帯も唐朝から賜与されたものだとしている。田中論文では基本的に直接入手したことを主張しているようにみえるが、丹後平古墳出土の獅噛式三累環頭大刀把頭のように伝世とか、まるいはまた何人かの人の手を経て伝わった可能性はないのであろうか。少し気になったところである。
以上のように、当地で馬産が9世紀末から存在し、都の貴重品が当地まで流れてきていることが確認された。それをふまえた上で第二部歴史学的考察に入る。ここでは論文・コラム各3本を収める。
最初の倉本一宏・堀井佳代子「藤原道長と馬、そして尾駮の駒」はまさに歴史学的研究の本丸に当たるものになる。ここでは尾駮の最古の史料である和歌について論じ、あわせて時の権力者藤原道長との間の深い関係について解説する。尾駮は地名でもあり毛色でもある(尾駮を斑模様と解することは第三部の山口論文に詳しい)。地名だとしても、一般には尾駮はみちのくのどこかにあると考えられており、尾駮の牧は空想上の牧であるとする。ここで述べられていることは、本稿冒頭で触れた、私自身のこれまでの見解と全く同じことである。つまり文献史学ではここまでしか言えないということがあらためて確認される。
ついで中世期に入る。伊藤一允「建武期の糠部と尾駮の牧」は、中世期について、現存する豊富な南部家文書等について従来の「津軽より」の解釈をあらためる別な解釈を提唱する力作。ただ伊藤が批判の対象として引用している解釈には、比較的影響力のある近年の学者の新説が多い。新説なので目立って、したがって気になるのであろうが、まだ定説ではないものが多々ある。たとえば伊藤が力点を置いている「中浜御牧・湊」(安藤宗季譲状・北畠顕家袖判御教書)の解釈も、学界ではまだまだ諸説あるのであって、批判する十三湊説が通説ではない。伊藤説も可能性はもちろんあるが、この文書についてはほかの解釈も十分ありうる。たとえば「なかはま」=「長浜」と解する点は、「中浜」表記が確実にある以上、難しいように思う。さらなる検討が必要であろう。また次の入間田論文冒頭で論じられているように鎌倉期は津軽に中心があったことは、中世期の北奥を論じる上で、おさえておく必要がある。
入間田宣夫「「尾駮牧」「糠部駿馬」をめぐる人・物・情報の交流について」は、いかにも氏らしいかなり刺激的な論文。その度合いは本書中第一である。 私にはこうした論の展開はできない。ただただ仰ぎ見るばかりである。氏は、時には古代にまで遡りながら、糠部を中心とした南北世界のつながりを詳細に論じた自身の研究をベースに、本書に収められた先行するフォーラムの成果を十分に消化合体させて、最終的に「「尾駮牧」が糠部は七戸の辺りにあったことについてはほぼ確実。といえるでしょうか。(中略)そのことについては、ほとんど疑いの余地なし。といえるでしょうか」とする。この「といえるでしょうか」が付されている点が微妙なところであるが、したがって著者の真意がどこにあるかは必ずしもはっきりしないが、率直な感想をいえば、残念ながらまだ「確実」ではないと思う。もちろん入間田論文については古代史の側から見ればなお検討すべき点が多いとはいえ、七時雨峠越えを「政治的ルート」とみること、民間の交易ルートとしての日本海側、太平洋側のルートのそれぞれの解明、そして関連しての北奥地域をすべて平泉を中心に考える研究への批判などは学ぶべき点が多々あることはいうまでもない。
ただ伊藤論文にせよ、入間田論文にせよ「尾駮」の地名を中世にまで無条件に引き上げて検討しているようにみえるが、そのこと自体検討の対象であることは本稿冒頭に書いたとおりである。歴史学者としての立場からすると、ここはやはり個人的には慎重にならざるを得ないところである。入間田が見出した永正5年の「馬焼印図」に、肝心の尾駮牧がないことも気になるところである。
最後の第三部は、文学的考察。尾駮が文学作品に見える語であることから、第二部の倉本・堀井論文とならんで、この問題ではやはり本丸に位置するところである。
飯沼清子「平安貴族と馬」は、古代王朝貴族の記した古記録類を博捜して、そこに見える馬の諸相を多面的に引き出したもの。古代貴族と馬の関係がじつに生き生きと描かれている。ただし古記録類には尾駮の語は見えないので、ここでも尾駮について触れるところはないのは当然である。
山口博「ユーラシアを西から東へ駆けた斑動物たち、そして尾駮の駒へ」は、尾駮駒を斑馬であるとした上で、ユーラシア大陸全域の史資料を博捜し、最終的に斑馬=尾駮駒を聖獣だとする壮大なスケールを有する大変興味深い論文。尾駮の駒の初出である『後撰集』詠み人知らずの歌も、本来それは荒れ馬ではなく良馬であると力説する。
つづく山口博「歌語“尾駮の駒”を育んだ王朝歌人集団」は、歌語としての尾駮の駒を流布させたのは藤原兼家と橘氏等陸奥と関係あるグループであり、やがて神聖な馬という本来の観念は失われ荒れ馬として理解されるようになるとする。
そして最後に山口博「王朝歌人の陸奥心象風景と現実」で結ぶ。尾駮については斑説を再論し、地名ではないと最終的に断案する。歌枕として、陸奥を美化して礼賛する心象風景が形成される過程を論じ、陸奥へ行ったことのない都人の幻想と、一方で実際に陸奥へ下向する国司たちの「泣きの涙」、恐ろしい人の国としての陸奥が交錯しているという。
六ヶ所村にとっては残念な結論ではあるが、和歌文学研究においては相当確度の高い結論になっている。
むすびにかえて
重厚で多面的なとても興味深い論考が展開された本書を読み終えての私の感想であるが、結論的には、入間田の希望的ないし慎重な言い回しにもかかわらず、やはりまだ実態としての「尾駮の駒・牧」が六ヶ所村の地にありました、と断定するのは、個人的には躊躇される、というのが率直なところである。ただし本書を読み終えて、しばし満足感に充足されたのも事実である。研究は確実に進歩している。それは間違いない。本書の書名が『尾駮の駒・牧を探る』ではなく『尾駮の駒・牧の背景を探る』となっているのもそうしたことを踏まえた用意周到な準備ではなかったかと思う。尾駮の駒がどこにあったのかとは関係なく、六ヶ所村の地が9世紀にまで遡る馬産の地であり、そして当地と南方(直接都との交流であるかどうかは断案できないが)との南北交流は確実に存在し、それが中世にまでつながる大動脈であった。それだけでも北方研究的には驚くべき成果である。こうした貴重な書が刊行されたことを斯界の関係者と共に大いに喜ぶとともに、今後の研究のますますの進展を期待したい。ねがわくば当地での考古学的文字資料の出土発見を!
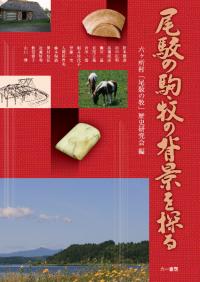
尾駮の駒・牧の背景を探る
著書:六ヶ所村「尾駮の牧」歴史研究会 編
発行元: 六一書房
出版日:2018/07
価格:¥2,750(税込)
目次第一部 考古学的考察
松本建速 六ヶ所村に馬はいつからいたか?
田中広明 東北地方北部出土の石帯とその背景
高橋照彦 東北地方北部出土の緑釉陶器とその歴史的背景
瀬川 滋 コラムI 陸奥湾東岸域(野辺地地区)の環濠集落
長尾正義 コラムII 三沢市「平畑(1)遺跡」の特徴について
第二部 歴史学的考察
倉本一宏・堀井佳代子 藤原道長と馬、そして尾駮の駒
伊藤一允 建武期の糠部と尾駮の牧
入間田宣夫 「尾駮牧」「糠部駿馬」をめぐる人・物・情報の交流について
藤木保誠 コラムIII 平安時代の都の馬事情
栗村知弘 コラムIV 糠部郡内の十烈、流鏑馬
近藤好和 コラムV 日本前近代の馬
第三部 文学的考察
飯沼清子 平安貴族と馬
山口 博 ユーラシアを西から東へ駆けた斑動物たち、そして尾駮の駒へ
山口 博 歌語“尾駮の駒”を育んだ王朝歌人集団
山口 博 王朝歌人の陸奥心象風景と現実
飯沼清子 コラムVI 巡方瑪瑙帯とその後
